| 西芳寺(苔寺) 池泉回遊式・枯山水 鎌倉・室町時代 |
| 京都市西京区松尾神ケ谷町56 電話:075−391−3631(事前予約して写経が必要) |
| 沿革 1249年中原師員(もろかず)は出家して行厳と号したが、それ以前にこの地に欣求浄土、厭離穢土を主題とした西方寺、穢土寺を創った。その後親秀が1339年に夢窓国師を請じて、上記二寺を浄土宗から禅宗に改め西芳寺とした。 庭園の構成 池泉部の西方寺(欣求浄土)部分には島が三つあり大和絵風の様式がそのまま残っている。但し作庭のバイブルと言われる「作庭記」では島姿の様々をいふ事の条で「霞形は池の面を見渡せば浅緑の空に霞の立渡れるが如く、二重三重にも入違えて細々とここかしこ、たぎれ渡り見ゆべきなり。これも、石もなく植木もなき白州なるべし」、つまり大和絵の霞がたなびいているさまを表すため、島々に白州を敷いて表現しようとしている。よって、苔はあってはならないのである。後世石組みに強い影響を与えた三尊石は長島にあるが夢窓国師により付け加えられたのだろう。なおここには鹿苑寺、慈照寺にあるような各種楼閣や反橋などがあったが、応仁の乱で消失した。 山畔上の穢土寺(厭離穢土)部分には空前絶後といわれる枯山水がある。この三段の滝は修行の場として龍門瀑と楞伽窟(りょうがくつ)の両故事に基づいて創られたのである。このことより日本庭園は一気に精神性を秘めたものになったのである。この滝の他に龍渕水は蹲踞(つくばい)の基になるなど影響が大きい。 作庭記の島姿の様々を言う事の章には次のように書いてある 一、霞形は、池の面を見渡すと、朝みどりの空に、霞の立ち渡った様に、二かさね三かさねにも入れ違えて、細々とここかしこがとぎれ渡って見えねばならない。これも、石もなく植木もない白洲であるべきである。 一、すはま形は、普通の州浜の様にするのである。但しあまりきちんと紺の紋などの様になるのはよろしくない。同じ洲浜形であるけれども、或いはひきのばしたように、或はゆがめたように、或いは背中合わせにうちちがえた様に、或いは洲浜の形かと見えるけれども、やはりそうではない様に見えなければならない。これに砂を散らした上に、小松などを少々植えるが良い。 |
▲先ず目に入る風景 |
 ▲夜泊石とも言われているが反橋の橋脚基礎とも考えられる 西芳寺の邀月橋(ようげつきょう)については朝鮮通信使が1443年にここを訪ね「橋の上にいると、まるで鯨の背中に乗って、大海原に浮かんでいるようだった」と感激している。夢窓国師が作ったこの橋は同じく彼の作った多治見市の虎渓山永保寺に同じ形と思われる無際橋といわれる反橋がある。 なお、金閣寺に拱北廊(きょうほくろう)、銀閣寺には龍背橋があったが、いずれも西芳寺の邀月橋に倣って作られた。 |
▲先ず掃除、次にお経 この右側にかつては瑠璃殿が建っていた |
 ▲鑓水は複雑な形をしている、奥に見えるのは現在の湘南亭 |
▲長島の三尊石組 作庭記では島は苔ではなく「石もなく植木もなき白州なるべし」である この形は金閣寺、銀閣寺、二条城、三宝院などの三尊岩組の基準になる。詳しくは三尊岩組参照 |
▲三尊石を横から見ると |
 ▲長島は苔に覆われているが本来は白砂で覆われていた。 |
▲亀島 ▲蓬莱島 |
 |
▲夕日ケ島の北側と岩島の上には湘南亭が建っていた |
 ▲鮮やかな新緑 |
 ▲通称 苔寺のゆえん |
 ▲ビロードのような苔 |
 ▲入り江には一艘の小舟が |
▲錦秋 |
▲かつては阿弥陀堂が建っていたところ、西芳寺になってからは本堂(西来堂)になった |
▲通宵路(つうしょうろ) 向上関(門)から頂上の縮遠亭までの四十九めぐりの急な坂道 熊秀才(ゆうしゅうさい)亮座主を慕って登ったという故事にもとづいている |
 ▲上段にある亀島を後ろ側から見る。亀頭石が立っている |
▲上記亀島を横から見ると亀頭石が三尊石組に見える。後世亀甲石のモデルになる |
 ▲供隠山枯滝石組 この庭を作った夢窓国師は「釈迦は修行すべき場所として『山林の樹下や巌穴の中などの草庵や露地に座すべき』としている」のように、山林に座禅を組み上中下と三段階の修行を行うことにより、自分の心の分別と進み具合を見定めてゆくべき、と考えていた。手前の岩の塊の前にある空地には約10人ほどが坐禅を組め、中段(写真中央)には5〜6人が坐禅した。上段者は上段の滝にある二つの坐禅石に座った。即ちこの滝は三段よりなる龍門瀑の故事と関連させて修行の場所として作ったものである。この枯滝石組は斎藤先生の「図解日本の庭」によると日本庭園史上、最も雄渾で力強く空前絶後の滝と記されている。 左下にいる鯉は初段を登り中段の滝に向かって遊泳中 当龍門爆は東光寺の滝と共に枯山水形の龍門爆の元祖といえる この滝は銀閣寺の山上部石組(西指庵横)に影響を与えた |
 ▲一段目の滝を登り二段目の滝へ |
▲遊泳中の鯉魚石 |
▲龍渕水と坐禅石 坐禅石は多治見市にある虎渓山永保寺の坐禅石(夢窓国師25年前の作)をモデルとして作られた。 龍渕水は金閣寺の銀河泉や銀閣寺の相君泉に影響を与えた。 |
 ▲龍淵水は蹲踞の源流である。 坐禅石の横にある泉で禅僧は心身を清めた |
 ▲蹲踞の原点 前石は一般的であるが鏡石は写真のように山畔の土砂を止めるためのもの |
 ▲上から見た蹲踞 |
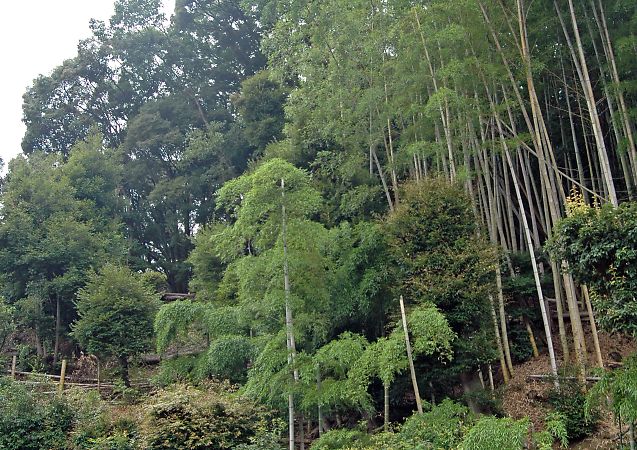 ▲縮遠亭跡推定地 延朗上人旧跡地背後(飛田範夫 「庭園の中世史」62頁 吉川弘文館) |
  ▲縮遠亭跡付近より京都市街地を望む ▲縮遠亭跡 |
| 総合TOP ヨーロッパ紀行TOP 日本庭園TOP |